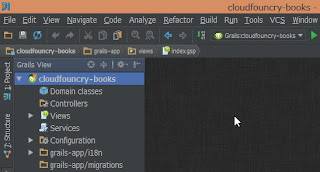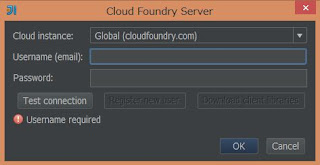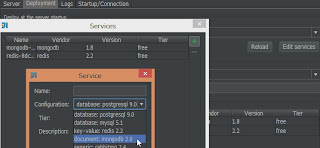G* Advent Calendar、6日目いってみます。
今日を境に、公開Grailsプラグインの数が爆発的に増える……といいなーという感じで
- Grails version
- 2.0.0.RC1
Grailsプラグインのリポジトリには、Maven形式のリポジトリが使用できます。
つまり、MavenのリモートリポジトリをGithub上に構築する以下の手法を使えば、GraisプラグインのリポジトリをGithub上に持てるわけですね。
Github を Maven 公開リポジトリにする
GitHub を Maven 公開リポジトリにする (Gradle 編)
何ができるの?
例えば、私はGrailsのAWSプラグインにパッチを当てたものをGithub上に公開しています。1
このプラグインは、次のようにしてどこからでも使用できます。
// grails-app/conf/BuildConfig.groovy
// ...
grails.project.dependency.resolution = {
// ...
repositories {
grailsPlugins()
grailsHome()
grailsCentral()
// ...
// Github上のマイプラグインリポジトリを指定
mavenRepo "http://literalice.github.com/maven-repo/releases"
}
}
# 上で指定したプラグインリポジトリからプラグインをインストール
cd grails-project
grails install-plugin aws 1.2.12.1.p1
とまあ、このように、改造したり開発したりした非公式オリジナルプラグインを簡単に公開して使えるようにしちゃおうというのが目的です。
GrailsのプラグインはzipファイルのURLを指定してインストールできるので他にいくらでも方法はあるわけですが、不特定多数に公開して良いなら今のところこれが一番手軽なんじゃないかなぁと。
この記事は、私がAWSプラグインを改造して公開したときの手順を思い出しながら書いていますが、オリジナルのプラグインを公開するときも同じような感じです。
以下がその手順です。
プラグインのソースコードを入手する
- Github上にあるプラグインのソースコードをフォークして、手元にクローン
- grails create-plugin コマンドでプラグインプロジェクトを作成する
- などなど
プラグインのバージョン番号を更新する
既存のプラグインを改造する場合は、バージョン番号がオリジナルのものと被らないように変更しておいた方が良いでしょう。1.0.0.p1、といった風に適当なサフィックスを付けておきます。
// XXGrailsPlugin.groovy - プラグインディスクリプタ
// ..
def version = "1.0.0.p1"
// ..
GrailsのReleaseプラグインをインストールする
プラグインのビルド、リポジトリへの公開は、このReleaseプラグインを使います。
Grails2系のcreate-pluginでプラグインプロジェクトを作成した場合は既にプロジェクトにインストールされているかと思いますが、そうでなければ自分でインストールする必要があります。
install-pluginコマンドでインストールせず、必ずBuildConfig.groovy上でプラグインを追加してexport設定を追加します。そうでないと、このマイプラグインをインストールしたときに、インストール先のプロジェクトもreleaseプラグインに推移的に依存するようになってしまいますので。
ちなみにAWSプラグインはinstall-pluginでreleaseプラグインをインストールしていたようなので、改造版ではこちらも修正しています。
// grails-app/conf/BuildConfig.groovy
// ...
grails.project.dependency.resolution = {
// ...
plugins {
// ...
build(':release:1.0.0.RC3') {
export = false // このプラグインはインストール先のプロジェクトには不要
}
}
}
プラグインをがしかし実装
プラグインをオレオレに改造します。がしかし好きな機能を実装します。
Github上にMavenリポジトリを構築する
好きな機能は実装できましたか? ではプラグインを公開しましょう。
Github を Maven 公開リポジトリにする
を参考に、MavenリポジトリをGithub上に構築します。
おおざっぱに言えば、
- ローカルにフォルダを作ります(「D:\mvn」など)。
- そのフォルダをgitのリポジトリとして初期化します。
- そのリポジトリに「gh-pages」という名前のブランチを作ります。
- 作った「gh-pages」ブランチをgithubにプッシュします
- おわり
後は、このフォルダにMavenリポジトリ構造でファイルを追加してプッシュすれば、Github上にそのファイルを公開できるわけですね
ここでは、「D:\mvn」にgitのリポジトリを作ったものとします。
ローカルフォルダにGrailsプラグインをリリースする
先ほどgitリポジトリとして初期化したフォルダ「D:\mvn」にプラグインをリリースします。
Grailsのreleaseプラグインは、SubversionリポジトリやリモートのWebDAV Mavenリポジトリにプラグインをリリースできますが、ローカルにはき出すことも可能なようです。
リリース先の指定方法はreleaseプラグインのマニュアルに載っています。
プロジェクトのBuildConfig.groovyか、ユーザーのホームディレクトリにsettings.groovyというファイルを置いて設定することができます。
バージョン管理に入れるであろうBuildConfig.groovyに、ローカルのファイルパスを書き込むというのはダサい気がするので、私はsettings.groovyを使いました。以下のように設定します。
// ~/.grails/settings.groovy
grails.release.scm.enabled = false // プラグインのソースコードはリリースしない
grails.project.repos.default = "localRelease" // リリース先未指定時のリリース先
grails.project.repos.localRelease.url = "file:///D:/mvn" // リリース先"localRelease"のURL
設定が終わったら、プラグインのプロジェクトディレクトリに移動して、リリースコマンドを実行します。2
cd my-grails-plugin
grails publish-plugin
コマンドが正常に終了すれば、「D:\mvn」にプラグインのzipファイル、pomファイルなどが生成されているはずです。3
MavenリポジトリをGithubにプッシュ
「D:\mvn」に生成された全てのファイルをコミットし、github上にプッシュします。
これで、作成したプラグインをどこからでも使用できるようになりました。
公開したプラグインを使う
公開したプラグインは、前述のように「BuildConfig.groovy」にGithub上のプラグインリポジトリを追加すれば使用できます。
リポジトリのURLは、Githubユーザー名が「literalice」、プッシュしたMavenリポジトリのフォルダ名が「mvn」であれば、「http://literalice.github.com/mvn」となります。
// grails-app/conf/BuildConfig.groovy
// ...
grails.project.dependency.resolution = {
// ...
repositories {
// ...
// Github上のマイプラグインリポジトリを指定
mavenRepo "http://literalice.github.com/mvn"
}
}
# 上で指定したプラグインリポジトリからプラグインをインストール
cd grails-project
grails install-plugin myplugin 1.0.0.p1
Twitterとかで通知
使って欲しい人に向けて、プラグインのリリース情報を通知します。プラグインリポジトリのURLとプラグイン名、プラグインバージョンを教えてあげれば大丈夫なはず。
まとめ
これでもう、プラグインのバグ修正も機能追加も待つ必要ないですね。直して公開です。
わざわざGrailsの公式リポジトリにプラグインを公開する必要もないですね。プラグイン名とリポジトリのURLを一緒に教えてあげれば大丈夫です。
気が向きましたら、本家にpull requestとか、プラグインを公式リポジトリに公開とかするとよりナイスですね。
Githubの最大容量は300MBらしいですが、普通のプラグインはそんなに容量大きくならないので大丈夫じゃないでしょうか、多分。
G* Advent Calendar、7日目は@masanobuimaiさんです。
注1: AWSプラグインは、GrailsからAmazon Web Serviceを簡単に使えるようにするものですが、SESでメールを送信するときに文字セットを指定できなかったためパッチを当てて使っています。
注2: 本来であれば、
cd my-grails-plugin
grails publish-plugin --repository=localRelease
とすることで、リリース先を明示的に指定できるはずなのですが、私の環境ですと上手く動かなかったので、デフォルトのリリース先をsettings.groovyで設定して、リリース先を指定せずにリリースできるようにしています。
注3: 「WARNING: unknown protocol 'file' for repository」というワーニングが出るのが気になりますが…とりあえず、問題なくリリースできるようです。